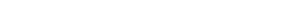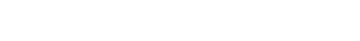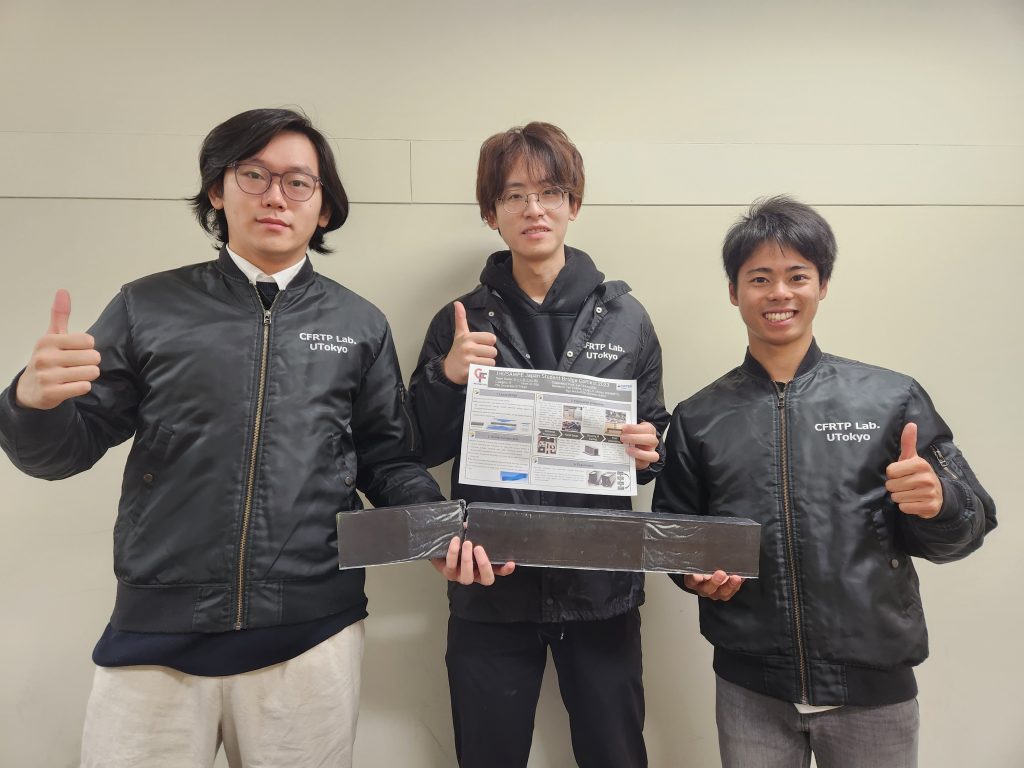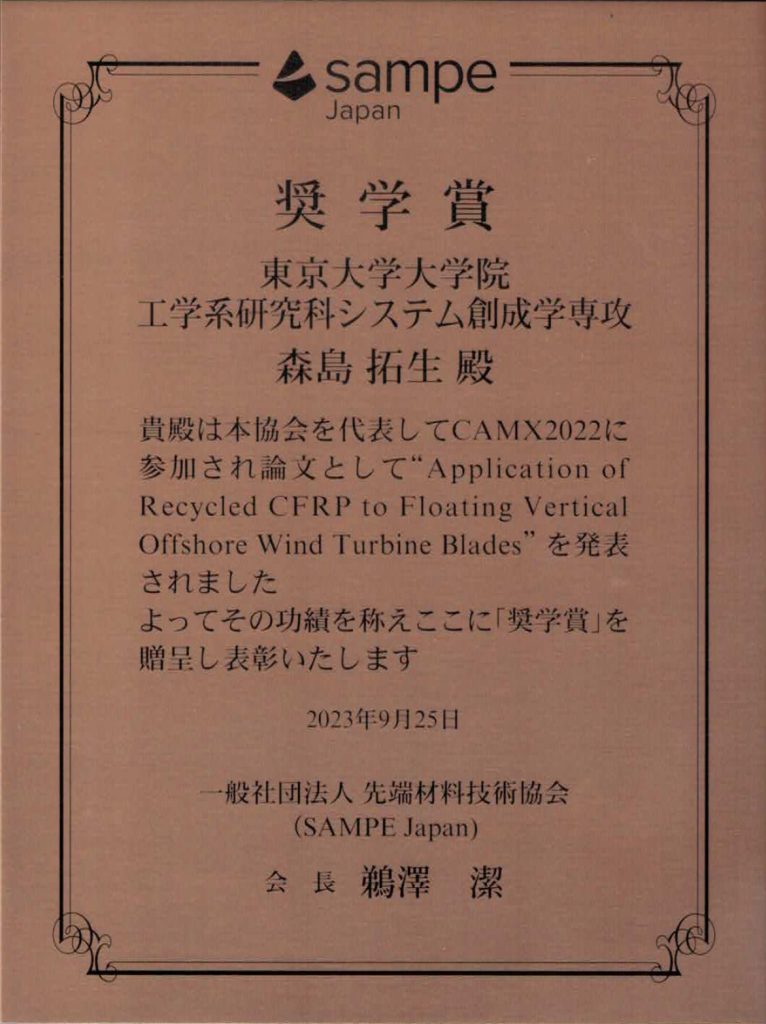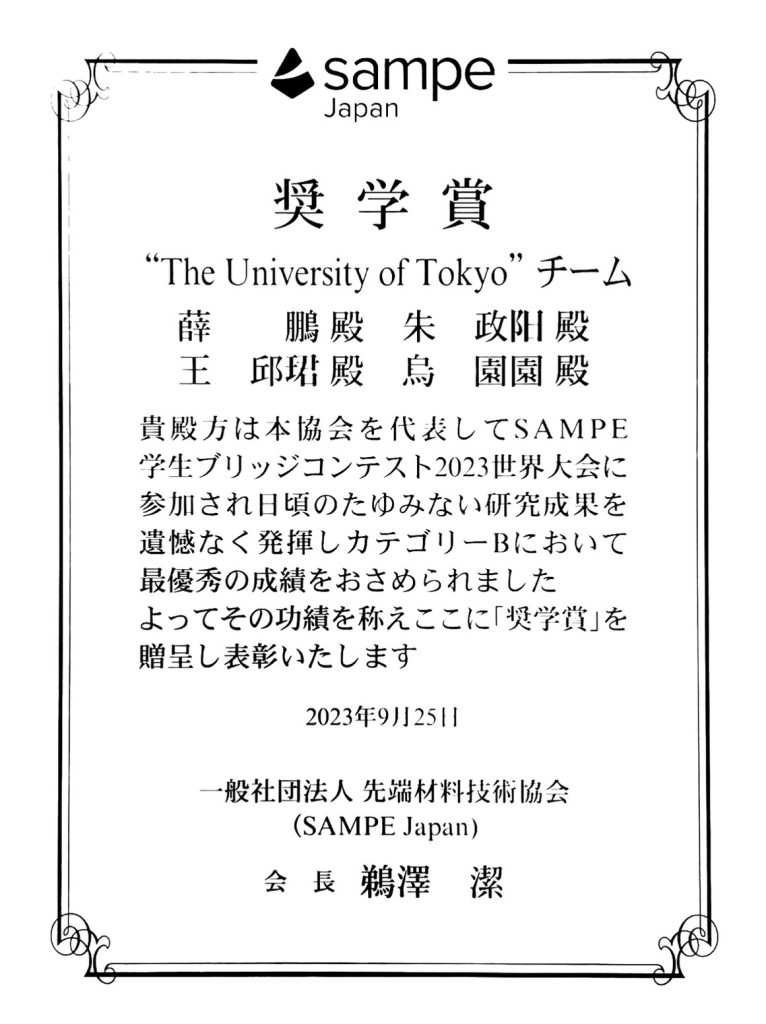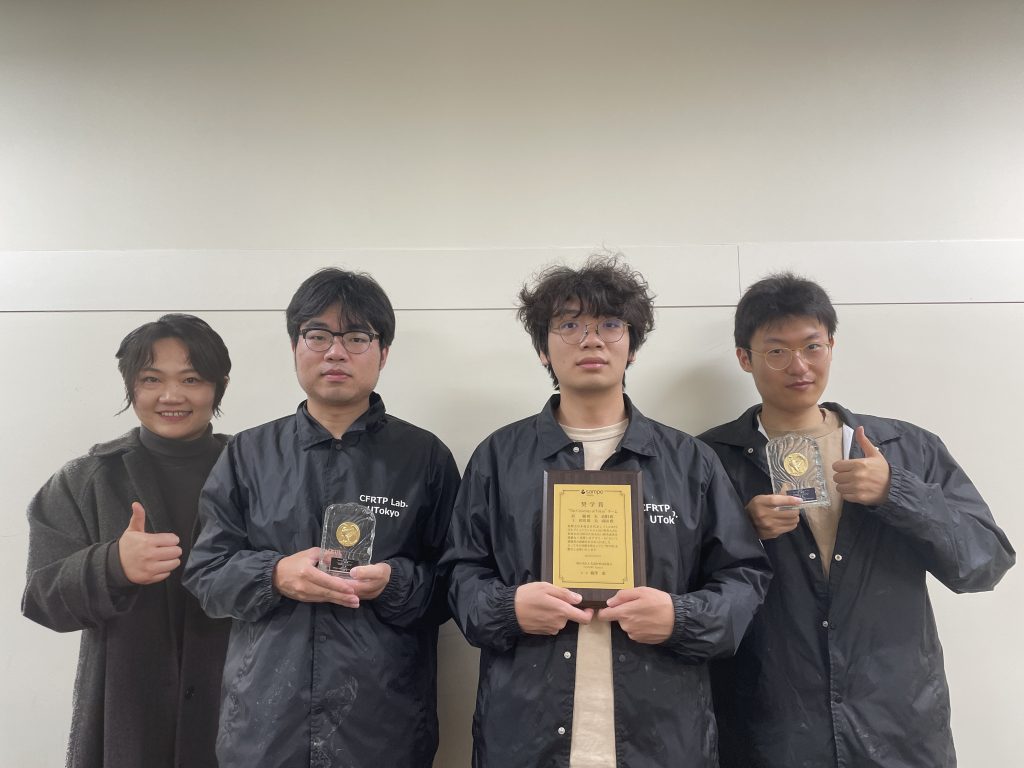概要
加藤・中村・安川研究室の小笠原光基さん (M2),佐々木航さん (M1),松波亮佑さん (M1) が,日本地質学会においてそれぞれ学生優秀発表賞を受賞しました。
受賞者氏名・所属
小笠原光基 (システム創成学専攻修士2年),佐々木航 (システム創成学専攻修士1年),松波亮佑 (システム創成学専攻修士1年)
賞の説明
日本地質学会第130年学術大会 学生優秀発表賞
研究・活動の説明
小笠原光基
・タイトル:Re-Os年代測定法に基づく兵庫県明延鉱床における鉱化時期の検討 ・概要:持続可能な社会を実現するために必要となる様々な金属の供給を確保するために、新しい鉱床の発見が世界的に重要視されています。鉱床の形成は地下のマグマ活動と密接な関わりがあると言われていますが、その詳細は明らかになっていません。優良な鉱床の形成プロセスが解明されれば、同様の地質学的条件を手がかりとして、新たな有望鉱床の発見に繋がることが期待されます。今回は、兵庫県の明延鉱床を対象に、マグマ活動と鉱床形成の因果関係を明らかにするべく、鉱脈が形成された年代をRe-Os放射年代法により高精度で決定しました。その結果、明延鉱床の形成年代は、これまで推定されてきた値よりも1000万年ほどさかのぼることが判明し、周辺の花崗岩質マグマとの密接な成因的関連性が新たに示唆されました。
佐々木航
・タイトル:後方散乱強度ヒストグラムのピークフィットと海底画像の解析に基づく南鳥島周辺におけるマンガンノジュールの分布様態
・概要:マンガンノジュールは、二次電池の重要な原料であるコバルトやニッケルを高濃度で含有し、新しいレアメタル資源として注目を集めています。2016-17年に南鳥島周辺でのマンガンノジュール分布調査が行われ、マルチナロービーム音響測深機による海底面の後方散乱強度調査と「しんかい6500」を用いた潜航調査が実施されました。先行研究のMachida et al. (2021) は、得られた後方散乱強度データを解析し、マンガンノジュールの密集域を示す強度閾値を明らかにしました。しかし、データのヒストグラムに見られる明瞭な複数のピークと海底面の特徴との関係は未解明のままでした。本研究では、これらのピークと海底面の特徴との関係を探るため、ピークフィット解析を行いました。さらに、「しんかい6500」で得られた海底画像を併せて解析し、各ピークとマンガンノジュール分布の関係を調べました。これにより、海底面からの音響反射がマンガンノジュールの分布様態とどのように対応しているかを明らかにしました。
松波亮佑
・タイトル:海洋-堆積物間のNd質量収支ボックスモデルに基づくレアアース泥生成の支配因子の長期変動の検討
・概要:新規資源として開発が期待されているレアアース泥の有望海域の選定には,その成因の理解が重要です.本研究では,モーターや発電機に不可欠な強力磁石の原料として産業上重要であり,レアアースの代表的な元素であるネオジム (Nd) を対象とした新たな数理モデルを構築しました.本モデルでは,海洋と深海堆積物の間でのNdの質量収支を定量化し,感度分析および長期シミュレーションを行うことで,太平洋の全域におけるレアアース泥生成の支配因子とその長期的な変動を定量的に検討しました.その結果,堆積速度および大陸縁辺域から海洋へのレアアースの流出がレアアース泥の品位に大きな影響を与えること,またダストフラックスの変動によって実際の遠洋性堆積物コア試料に見られるレアアース泥品位の増減の傾向を概ね再現できることが明らかとなりました.
受賞者コメント
小笠原光基
本賞の受賞にあたり、加藤先生をはじめとした同研究室の皆様や、研究にご協力していただいた兵庫県養父市の皆様、分析を実施させていただいている千葉工業大学の皆様、日頃から支援をいただいている服部国際奨学財団などに深く感謝いたします。このような栄誉ある賞をいただいたことを誇りに思う一方で、現状に満足せず研究を突き詰めて行きたいと感じている部分もございます。私の修士研究にはまだまだ解明すべき点が多くあり、それをできる限り解明するため、これからも気を引き締めて取り組んでいきたいと思います。
佐々木航
本賞の受賞にあたり、安川先生、中村先生、加藤先生、千葉工業大学の町田先生などサポートしてくださった方々に深く感謝いたします。修士課程での研究を評価していただき、またこのような栄誉ある賞をいただき大変誇りに存じます。本研究によって、船上からの音響探査により海底マンガンノジュールの資源分布・資源量推定を従来より詳細かつ効率的に行える可能性が示されました。今後は、機械学習を応用して画像分析をより高精度に行うことや、対応関係が生まれる理由の考察、他海域への適用可能性の検討などに取り組む予定です。今回の学生優秀賞をいただいたことに感謝しつつ、より一層研究に励む所存です。
松波亮佑
本賞の受賞にあたり,安川先生をはじめ,サポートいただいた方々に深く感謝いたします.これまでの研究成果を評価していただき,このような栄誉ある賞を頂けたことを大変誇りに思います.今回の受賞を励みに,今後も研究活動に精進してまいります.