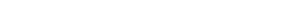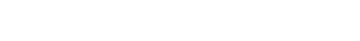専攻概要
工学知を統合し、自然や社会と調和のとれた革新的な「システム」の実現を目指す「システム創成学専攻」。 専攻長から進学を希望する皆様へのメッセージ、システム創成学専攻の教育理念、専攻理念をご案内いたします。
専攻長からのメッセージ
現代は大きな変革と課題の時代であり、それに応えるには学際的な知恵と創造力が求められています。本専攻は東京大学における改革と創造の流れの中で、複数の工学分野を統合することで誕生しました。
異なる工学の要素を組み合わせ、全体として調和のとれたシステムを構築し、社会に革新的な価値をもたらす。それがシステム創成学の使命です。単なる専門知識の寄せ集めではなく、社会や自然との関わりを俯瞰的にとらえ、分野を越えて結びつけていく。この総合的な視点こそが「システム創成学」の本質です。ここでの学びは、専門分野を深めると同時に、異分野を結びつけて新たな解決策を創り出す力を育むものです。
近年、科学技術の進歩はかつてない速度で進み、私たちの生活や社会を大きく変えています。とりわけ人工知能(AI)は数年前には想像できなかった領域に到達しました。なかでも生成AIは、文章や設計、プログラムなどを自動生成できる技術として急速に普及し、産業界においても導入が加速しています。一方で、通信技術も大きな転換期を迎えています。5Gが標準化された現在、すでに次世代の6Gが視野に入っています。超高速通信や超低遅延が実現すれば、サイバー空間と物理空間の融合、すなわち日本が提唱するSociety 5.0がさらに現実のものとなります。さらに非地上系ネットワーク(NTN)では低軌道衛星通信システムやHAPSによる地上と宇宙を統合したグローバルな接続の実現が進んでいます。また、量子コンピューティングの可能性も現実味を帯びてきました。量子ビットの安定化や規模拡大の成果により、実用化が視野に入っています。2025年は国連が定めた「国際量子科学技術年」であり、量子技術の革新が科学や産業を根本から変えることへの期待が高まっています。本専攻では、AI・通信・量子といった先端技術の研究だけでなく、それらを活用して社会課題を解決する仕組みづくりを重視しています。
本専攻はまた、人類と地球の関係が大きく変化していることにも真剣に向き合っています。記録的な豪雨や猛暑などの極端な気象現象は、人間活動が地球環境に大きな負荷を与えていることを示しています。こうした現実を前に、国際社会は持続可能でレジリエントな社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの拡大や温室効果ガス削減に本格的に取り組んでいます。世界では、再生可能エネルギーが新規導入され、電源拡大の多くを占めるようになっています。私たちに求められているのは、社会全体を変革するシステムとしての持続可能性の実現です。
環境課題に加えて、私たちの社会システムも大きな試練に直面しています。遠隔教育やテレワーク、オンライン医療などデジタルサービスの普及が加速しています。地政学的な緊張や紛争が資源・食料・エネルギーの供給に影響を与え、グローバルな相互依存の脆弱性が明らかになりました。現代社会はかつてないほど複雑かつ相互依存的です。気候変動、公衆衛生、地政学的リスクは相互に絡み合い、単独の技術や政策では解決できません。したがって、技術・経済・環境・社会を包括的にとらえたシステム設計が必要です。これこそがシステム創成学の役割です。
このような時代にあって、我が国は、科学技術と社会をつなぐリーダーの人材育成が急務です。必要なのは、深い専門性と広い視野を兼ね備えた人材です。単なる専門家の集合では解決できない問題に対して、分野横断的な視点から協働を導き、全体として正しい解へと導く力が求められます。本専攻の使命はまさに、そうした人材を育成することにあります。大学院での学びは、社会に出る前の最後の集中的な鍛錬の場です。夢や志を大切にしながらも、専門を深めつつ社会的課題への感度を磨き、信頼される人材として成長する、そして、その成果を社会に還元する姿勢を持つ人材を育成したいと考えています。
2025年10月
東京大学大学院工学系研究科
システム創成学専攻 専攻長
中尾 彰宏
システム創成学専攻の専攻理念

新たな教育・研究を展開
システム創成学専攻では、人間、人工物、自然をとりまく様々な現代的課題に立ち向かえる人材を輩出するために、ものごとを多面的、俯瞰的視点から捉えるシステム科学を基礎として、専門領域に細分化された従来の工学知を統合し、自然や社会と調和のとれた革新的なシステムの実現のための原理と方法論に関する教育・研究を展開していきます。
新たな価値を創造
急速にグローバル化し、加速的に複雑化している現代社会において噴出する様々な課題を解決するためには、ものごとを多面的、俯瞰的視点から捉えるシステム思考が重要となってきています。 すなわち、対象を構成する基本要素を抽出、分析するといった旧来型の工学的貢献ではなく、要素間の関係性や相互作用を考慮しながら総合化し、個別の専門領域で培われた知識や技術を統合することによって、環境問題や安全安心社会の実現等、現代社会が直面する課題に対して具体的なソリューションを提供し、新しい価値の創出や革新的にシステムをイノベーションすることが新たに工学に求められているのです。 例えば、自然と社会、技術との調和を実現するためには、工業製品等の人工物ばかりでなく、ヒューマンウェア、マネジメント、サービス、社会制度等といった人工物を取り巻く環境への関与も必要となってきます。さらに、個別の人工物の設計製造を追求するだけでなく、それらの人工物が社会に与える影響や合理的な実装方法を考慮する重要性も日々増しています。また、個別の製品価値だけでなくそれらを取り巻く社会や環境の仕組みを全体的に再設計することで、他の追随を許さない総合的な価値を創出する可能性も期待されます。
新たな分野を開拓
工学が社会の期待に応え活躍の場をますます拡大していくために,システム創成学専攻は、工学知の統合、システム思考をベースに自然システム、人工物、社会システムの機能的融合を目指す工学の新分野を開拓していきます。
システム創成学専攻の教育理念

システム創成学専攻の教育目的
システム創成学専攻では、俯瞰的視点とシステム思考に基づき戦略的に意思決定を行う能力、特定専門分野におけるアナリシス能力を備え、俯瞰的視点から先端的要素技術の開発ができる人材、革新的なシステムの創出ができる人材の養成を教育目的とします。 修士課程においては、特定工学分野の基礎が確立できているとともに、システム科学の概念と方法論について十分に理解し、社会の各分野でシステム創成学の専門家として活躍できる人材の養成を主眼とします。 博士課程においては、さらに現実世界の中から自ら課題を発見し、その解決に向けてプロジェクトを企画立案し、そのプロジェクトのメンバーとして自己の専門知識と技能を有機的に活用して解決する能力を有するシステム創成学の高度専門家を養成するとともに、その一連のプロセスを科学的に分析し普遍化することのできる研究者を養成します。
システム創成学専攻のコアコンピタンス
システム創成学専攻では、以下の4つの力を育みます。
- 問題の本質を領域横断的、俯瞰的、かつ体系的に捉えるシステム思考能力。
- 複雑な現実問題を数理的、実証的アプローチが適用できる形にモデル化して解決する能力。
- 工学の特定専門分野において専門家として認知されるに十分な知識と技能。
- 自己を磨きつつ社会の中で人と関わりながら活躍できる人間力。

期待される卒業生像
卒業生の進路としては、ハード、ソフト、サービスを問わず産業界において新製品・新規事業の企画立案や、設計、生産、運用、管理の計画、実施に責任を有する指導的技術者・管理者、公共政策等の社会システムのデザインや決定、実施に責任を有する行政スペシャリスト、システム創成学や学際的学術分野の研究者等が想定されます。